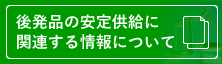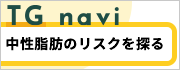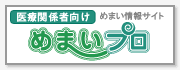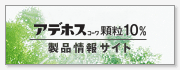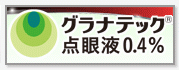リバゼブ配合錠の妊婦への投与について教えてください。
妊婦又は妊娠している可能性のある女性は禁忌のため、投与しないでください1)。
リバゼブ配合錠の承認までの臨床試験では妊婦又は妊娠している可能性のある女性は対象から除外しているため使用経験がなく、安全性は確立していません2)。
ピタバスタチンでは、動物実験(ラット)での周産期及び授乳期投与試験(1mg/kg以上)において分娩前又は分娩後の一時期に母動物の死亡が認められています。また、ウサギでの器官形成期投与試験(0.3mg/kg以上)において母動物の死亡が認められています。ラットに他のHMG-CoA還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されています。更にヒトでは、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤で、妊娠3ヵ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告があります2)。
<参考>
■ラット周産期及び授乳期投与試験2)
ラットにピタバスタチンの0.1mg/kg/日、0.3mg/kg/日、1mg/kg/日、3mg/kg/日、10mg/kg/日、30mg/kg/日を妊娠17日から分娩後21日まで経口投与した結果、母動物では30mg/kg/日群で体重増加抑制、摂取量の減少が認められ、1mg/kg/日以上の群で死亡が認められました。出生児では1mg/kg/日以上の群で生後4日の生存率の低下が認められ、10mg/kg/日群で体重増加抑制、歯芽萌出の発現率低下が認められました。
■ウサギ器官形成期投与試験2)
ウサギにピタバスタチンの0.1mg/kg/日、0.3mg/kg/日、1mg/kg/日を妊娠6日から18日まで経口投与した結果、0.3mg/kg/日以上の群で流産及び母動物の死亡が認められました。
■血液-胎盤関門通過性(ラット)
〇ピタバスタチン3)
胎盤通過性は小さく、代謝物の胎児移行もほとんどないものと考えられました。
①組織内放射能濃度(妊娠18日目ラット)
妊娠後期(妊娠18日目)のラットに14C-ピタバスタチンカルシウム1mg/kgを単回経口投与し、母体及び胎児中の組織内放射能濃度を測定したところ、母体組織では肝臓の放射能濃度が最も高く、心臓、腎臓及び乳腺にも分布が認められました。胎児全身放射能濃度は、母体血漿中放射能濃度と比較して低い結果でした。
②全身オートラジオグラム(妊娠18日目ラット)
妊娠18日目のラットに14C-ピタバスタチンカルシウム1mg/kgを単回経口投与し、投与後1時間の全身オートラジオグラムを作成したところ肝臓、消化管及び腎臓等に高い放射能が認められましたが、胎盤及び羊水中への放射能の分布は少なく、胎児への移行はほとんど認められませんでした。
〇エゼチミブ4)
胎盤を通過することが確認されています。
妊娠18日目の雌ラットに[14C]エゼチミブ10mg/kgを単回経口投与した時、母動物における組織中放射能は大部分の組織で投与後4時間に最高値を示し、乳腺、子宮、胎盤、羊水及び羊膜いずれも定量下限未満でしたが、卵巣は母動物の血漿中放射能濃度の約1/3レベルの放射能が検出されました。胎児血液及び胎児の主要臓器(肝臓、腎臓、肺、心臓及び脳)についてはいずれも定量下限未満でした。
生殖発生毒性試験における上限投与量(1000mg/kg/日)を雌ラットの妊娠6~20日に反復投与した時、エゼチミブの胎盤通過性が確認されました。
リバゼブ配合錠の承認までの臨床試験では妊婦又は妊娠している可能性のある女性は対象から除外しているため使用経験がなく、安全性は確立していません2)。
ピタバスタチンでは、動物実験(ラット)での周産期及び授乳期投与試験(1mg/kg以上)において分娩前又は分娩後の一時期に母動物の死亡が認められています。また、ウサギでの器官形成期投与試験(0.3mg/kg以上)において母動物の死亡が認められています。ラットに他のHMG-CoA還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨格奇形が報告されています。更にヒトでは、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤で、妊娠3ヵ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告があります2)。
<参考>
■ラット周産期及び授乳期投与試験2)
ラットにピタバスタチンの0.1mg/kg/日、0.3mg/kg/日、1mg/kg/日、3mg/kg/日、10mg/kg/日、30mg/kg/日を妊娠17日から分娩後21日まで経口投与した結果、母動物では30mg/kg/日群で体重増加抑制、摂取量の減少が認められ、1mg/kg/日以上の群で死亡が認められました。出生児では1mg/kg/日以上の群で生後4日の生存率の低下が認められ、10mg/kg/日群で体重増加抑制、歯芽萌出の発現率低下が認められました。
■ウサギ器官形成期投与試験2)
ウサギにピタバスタチンの0.1mg/kg/日、0.3mg/kg/日、1mg/kg/日を妊娠6日から18日まで経口投与した結果、0.3mg/kg/日以上の群で流産及び母動物の死亡が認められました。
■血液-胎盤関門通過性(ラット)
〇ピタバスタチン3)
胎盤通過性は小さく、代謝物の胎児移行もほとんどないものと考えられました。
①組織内放射能濃度(妊娠18日目ラット)
妊娠後期(妊娠18日目)のラットに14C-ピタバスタチンカルシウム1mg/kgを単回経口投与し、母体及び胎児中の組織内放射能濃度を測定したところ、母体組織では肝臓の放射能濃度が最も高く、心臓、腎臓及び乳腺にも分布が認められました。胎児全身放射能濃度は、母体血漿中放射能濃度と比較して低い結果でした。
②全身オートラジオグラム(妊娠18日目ラット)
妊娠18日目のラットに14C-ピタバスタチンカルシウム1mg/kgを単回経口投与し、投与後1時間の全身オートラジオグラムを作成したところ肝臓、消化管及び腎臓等に高い放射能が認められましたが、胎盤及び羊水中への放射能の分布は少なく、胎児への移行はほとんど認められませんでした。
〇エゼチミブ4)
胎盤を通過することが確認されています。
妊娠18日目の雌ラットに[14C]エゼチミブ10mg/kgを単回経口投与した時、母動物における組織中放射能は大部分の組織で投与後4時間に最高値を示し、乳腺、子宮、胎盤、羊水及び羊膜いずれも定量下限未満でしたが、卵巣は母動物の血漿中放射能濃度の約1/3レベルの放射能が検出されました。胎児血液及び胎児の主要臓器(肝臓、腎臓、肺、心臓及び脳)についてはいずれも定量下限未満でした。
生殖発生毒性試験における上限投与量(1000mg/kg/日)を雌ラットの妊娠6~20日に反復投与した時、エゼチミブの胎盤通過性が確認されました。
参考資料
1)リバゼブ配合錠LD/リバゼブ配合錠HD 電子添文 2023年7 月改訂(第3版) 2. 禁忌(次の患者には投与しないこと) 2.4
2)リバゼブ配合錠LD/リバゼブ配合錠HD インタビューフォーム 2024年8月改訂(第6版) Ⅷ.安全性(使用上の注意等)に関する項目 6.特定の背景を有する患者に関する注意 (5)妊婦
3)リバゼブ配合錠LD/リバゼブ配合錠HD インタビューフォーム 2024年8月改訂(第6版) Ⅶ.薬物動態に関する項目 5.分布 (2)血液-胎盤関門通過性
4)ゼチーア錠 インタビューフォーム 2023 年7 月改訂(第11 版) Ⅶ.薬物動態に関する項目 5.分布 (2)血液-胎盤関門通過性
作成年月
2024年9月